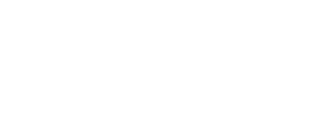Z世代とは?

Z世代とは、概ね1996年から2012年頃に生まれた世代を指し、英語では「Generation Z」と呼ばれます。この名称は、1965~1979年頃に生まれたX世代からはじまるアルファベット順の流れに由来しています。Z世代は、インターネットやスマートフォンが普及した環境で生まれ育っており、「デジタルネイティブ」として高いデジタルリテラシーを備えている点が特長です。
一般に「若者世代」というイメージが強いものの、1996年生まれの方々はすでに社会人としての経験を重ね、中にはマネジメント層として活躍しているケースもあります。なお、世代の区分には明確な定義がないため、Z世代の捉え方には若干の幅があります。
Z世代が注目される理由
Z世代が注目を集めている背景には、社会構造や価値観の変化が大きく関係しています。デジタル化の進展により、Z世代はSNSなどを通じて多様な情報や価値観に日常的に触れ、上の世代とは異なる考え方や行動スタイルを持つようになりました。少子高齢化や日本の経済状況の影響もあり、終身雇用や年功序列といった従来の働き方にあまりこだわらない点も特長です。
実際に働きはじめている方が多く、今後は労働市場や消費市場に大きな影響を与える存在になることが見込まれています。そのため、Z世代の価値観や行動パターンを把握することは、企業の採用戦略において欠かせない視点となっており、より柔軟かつ個人の志向に寄り添ったアプローチが求められています。
Z世代の大きな特長

SNSやデジタル環境とともに育ったZ世代は、X世代(1965~1979年頃に生まれた世代)やY世代(1980~1995年頃に生まれた世代。ミレニアル世代とも呼ばれる)とは異なる価値観や行動様式を持っています。次に、その特長を詳しく解説します。
ソーシャルネイティブである
Z世代は、インターネット環境が当たり前に存在する時代に生まれ育ち、スマートフォンやSNSに親しんできたソーシャルネイティブ世代です。幼い頃から、オンライン上での情報収集や他者とのやり取りを自然に行ってきました。SNSは単なるコミュニケーションツールではなく、自己表現や価値観の形成においても大きな役割を果たしており、以前の世代とはデジタルとのかかわり方が大きく異なります。
また、Z世代のデジタルリテラシーの高さは、SNSにとどまらず、メタバースやeスポーツ、オンラインゲームなど多様な領域に広がっています。さらに、最新技術への関心も高く、アデコ株式会社が実施したアンケート調査では、Z世代の2割以上が、業務で生成AIをほぼ毎日活用しているという結果が出ました。X・Y世代(1965~1995年)では1割強にとどまっているのと対照的です。
参照元: https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/334
このように、Z世代はデジタルの活用に積極的な行動特性を持つことから、採用や組織マネジメントにおいても、その特性を把握することが重要です。なお、Z世代については、以下の記事でも詳しく解説しています。
個性や多様性を大切にする
Z世代は、個性や共感を重視する傾向が強い世代です。他人と同じであることよりも「自分らしさ」を重視し、個々の価値観や生き方を尊重する姿勢が自然と根付いています。
この背景には、インターネットやSNSを通じて幼い頃から様々な文化・考え方・ライフスタイルに触れてきた経験があります。そのため、Z世代の多くは差別的な考えや排他的な態度に対して敏感であり、多様な人々と公平に接することを当たり前の価値として捉えています。
多様性を尊重する価値観は、ダイバーシティやインクルージョンといった社会的なテーマへの関心にもつながっており、企業や組織においても、こうした感覚を理解した対応が求められます。
Z世代の仕事に対する価値観
ここでは、Z世代が仕事に何を求め、どのような価値観を大切にしているのかを詳しく見ていきます。
給与・報酬・福利厚生を重視する
Z世代とX・Y世代の働き手を対象にした比較調査によると、勤務先を選ぶ際に最も重視するのは「給与・報酬」がどちらの世代でも1位でした。Z世代では38.6%、X・Y世代では41.5%と、およそ4割を占めています。「福利厚生」を挙げた人がZ世代では3位8.2%で、X・Y世代の7位3.3%よりも多くなっているのが特徴的です。
一方で、入社後には、人や社会への貢献や、自分の成長といった内発的動機を重視する傾向も見られます。Z世代は、物やサービスが豊富な時代に生まれ育った背景から、金銭や地位などの外発的動機への関心が、上の世代と比較して相対的に低いとされています。待遇面に加え、内面的な充実感や自己成長の実感を得られる職場環境が重要です。
柔軟な働き方を望む
Z世代は、仕事と私生活のバランスを大切にし、効率性を重視した柔軟な働き方を望むのが特徴です。通勤やオフィス勤務を非効率と捉える方が多く、アンケートでもリモートワークを希望する声が目立ちます。フレックスタイム制やリモートワークなど、タイムパフォーマンスを重視した選択肢が好まれています。
最新テクノロジーに対する抵抗も少なく、業務の効率化には前向きです。一方で、形式的な働き方や成果に直結しない残業には価値を感じにくいという特長もあります。Z世代にとって仕事は「生活を豊かにするための手段」であり、自分らしく働ける環境を重視する意識が強いと言えるでしょう。企業側には、こうした価値観の変化を把握した上で、柔軟かつ効率的な働き方を提案する姿勢が求められます。
転職や副業・兼業に積極的である
Z世代は、従来のように一つの企業に長く勤めることにこだわらず、自分に合った働き方やキャリアの選択肢を広げる考え方が浸透しています。アンケート結果からも、他世代に比べて転職への意欲が高く、副業や兼業にも強い関心を持っていることがうかがえます。
彼らが就職活動を行った時期は、終身雇用制度が崩れ始め、人材不足による売り手市場が続いていたという背景があり、一つの職場に長くとどまることを前提とせず、より柔軟なキャリア形成を志向する動きが強まりました。こうした意識の変化から、自分の成長や価値観に合わせて環境を変えることを前向きに捉える方が増えたと考えられます。
一方で、転職や副業への積極性が、「すぐに辞めるのではないか」という懸念につながることもあり、企業側の柔軟な受け止め方が必要です。
他世代よりも高い「仕事重視」志向
Z世代の中には、プライベートよりも仕事を重視する姿勢を持つ方が目立ちます。アンケートによると、「プライベートより仕事を優先したい」と回答した割合はX・Y世代で17.0%だったのに対し、Z世代では24.8%にのぼりました。この結果から、Z世代は他の世代に比べて仕事重視志向が強いことがうかがえます。
Z世代の能力を引き出すためのポイント
ここでは、Z世代の能力を十分に発揮してもらうためのポイントを紹介します。
働き方を選べるようにする
Z世代が仕事に求めることは効率性や多様性であり、働き方の選択肢が多い企業に魅力を感じます。リモートワークやフレックスタイム制など柔軟な制度を整えることで、Z世代の能力を引き出しやすくなるだけでなく、他世代にとっても働きやすい環境となり、離職率の低下や企業価値の向上にもつながるでしょう。
勤務時間や勤務場所に柔軟性を持たせることで、既存社員のエンゲージメントが高まり、生産性の向上も期待できます。個々のライフスタイルに合わせた働き方を可能にする体制づくりは、Z世代の採用力強化だけでなく、多様な人材の活躍を後押しする有効な手段です。
個性や価値観を否定しない
Z世代との信頼関係を築くには、個性や価値観を否定せず、一人ひとりを尊重する姿勢が欠かせません。安易に「若いから」「Z世代だから」とカテゴライズするのではなく、本人の考えや背景に目を向けるようにしましょう。
たとえば、上司が目の前にいるにもかかわらず、社内チャットを使って報連相を行うのは、デジタルネイティブであるZ世代にとって自然な選択であり、効率を重視する価値観の表れです。このような行動に戸惑うことがあっても、まずはその理由や背景を把握しようとする姿勢が重要です。
仕事での評価を明確にする
Z世代の力を引き出すには、仕事の評価基準を明確にすることが重要です。かつて主流だった年功序列型の評価制度が色濃く残る企業では、「社歴が長ければ偉い」「年齢を重ねている人ほど仕事に長けている」といった価値観が根強く存在するでしょう。
しかし、Z世代は性別や年齢に関係なく、公平で合理的な判断を重視する価値観を持っています。したがって、業績や成果に基づいた透明性のある評価制度を導入し、納得感のあるフィードバックを行うことが必要です。
まとめ
Z世代は、デジタルネイティブとして高いテクノロジー適応力を持ち、多様性や効率性を求める価値観を持っています。また、柔軟な働き方を望み、成果に基づく公平な評価を重視するのが特長です。
企業にとっては、Z世代の特長を把握し、個性を尊重する組織づくりを進めることが必要です。今後の労働市場の中心となるZ世代を生かすためには、柔軟性と透明性を備えた職場環境の整備が重要な鍵となります。
最新のセミナー情報、コラムなどを受け取りたい方は、下記からメールマガジンを登録してください。