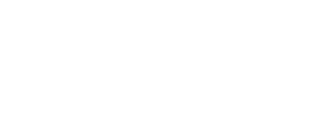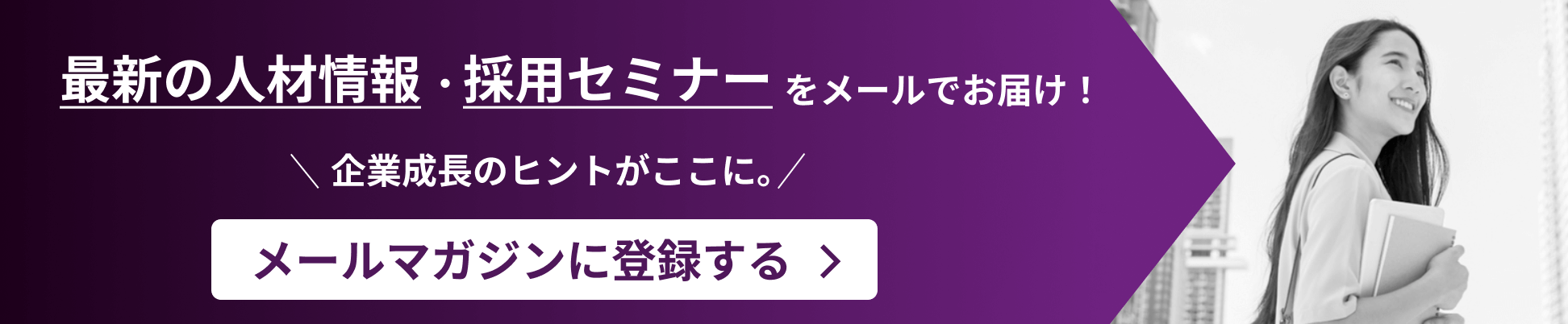採用のミスマッチが起こる割合

採用のミスマッチとは、企業と求職者の間で生じる認識のズレのことです。これは新卒・中途採用ともに起こり得ることで、早期退職や生産性の低下につながることから多くの企業で深刻な問題となっています。実際、厚生労働省の調査によると、2021年3月に卒業した新規学卒就職者の3年以内の離職率は、1000人以上の事業所規模の場合で高校卒が27.3%、大学卒が28.2%と、新卒社員の約3割が3年以内に辞めています。
このような採用のミスマッチは、採用や育成にかかるコストが無駄になるだけでなく、既存従業員の業務負荷が増えることで、モチベーション低下や優秀な従業員の流出など、さまざまな面で損失が生じます。また、人材が定着しないことは企業のイメージを悪化させ、さらには企業独自のノウハウが蓄積されず、継続が危ぶまれる可能性もゼロではありません。入社後の求職者にとっても本来の能力が十分に発揮できない状況が続き、心身の不調を招くおそれがあります。そのため、企業は採用のミスマッチを防ぐべく十分な対策を講じることが重要です。
参照元:
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html
段階別 採用のミスマッチが起こるおもな原因

採用のミスマッチが起こる原因はさまざまです。ここでは、採用前、採用中、入社後の3つの段階に分けておもな原因を解説します。
採用前:求職者に十分な情報提供が行われていない
採用のミスマッチの原因としてまず挙げられるのが求職者に対する情報提供不足です。求職者が企業について十分な情報が得られない場合、入社後に「こんなはずではなかった」というギャップが生じ、退職を選んでしまうことがあります。とくに就活生の場合、十分な企業研究ができていないまま採用選考が進んでしまうケースも少なくありません。具体的には、業務内容や給与条件、福利厚生、求めるスキル、組織文化、キャリアパスなどに関する情報が不十分だと採用後にミスマッチが起きる可能性が高まります。
採用前:メリットだけを伝えている
詳細な情報提供を行っていても、企業のいいところ(メリット)ばかりではミスマッチが生じます。優秀な人材を確保したいがために、メリットだけを伝えて魅力ある企業に見せたい気持ちはわかります。しかし、本来伝えるべき企業の課題や問題点を隠してしまうと、入社後に現実を知って早期退職につながりかねません。とくにZ世代は「口コミ世代」とも呼ばれ、企業の本当の姿を重視して就職先を決める方が多いため、入社前にデメリットを知らせることが重要です。
Z世代における「デメリットの開示」の重要性について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
採用中:採用基準が統一されていない
採用基準が統一されていない場合、面接担当の主観に任せてしまうことになり、採用のミスマッチが起こりやすくなります。なぜなら、面接官によって採用基準がバラバラでは、企業が求める人物像に合わない人材を採用してしまうリスクがあるからです。その結果、本当に必要な人材が確保できないだけでなく、事業計画や組織成長に支障をきたすおそれがあります。
入社後:フォローが不足している
入社後、求職者がスムーズに職場に適応するためには十分なフォローが欠かせません。しかし、十分なサポート体制ができていない場合、せっかく入社しても職場の雰囲気や働き方になじめず、早期退職してしまう可能性が高くなります。とくに中途採用の場合は、前職での価値観や業務スタイルが身についているため、新たな環境に馴染むには時間とサポートが必要です。早期に実力を発揮してもらうためにも、組織全体で受け入れ体制を整え、段階的かつ丁寧なフォローを行うことが重要です。
採用のミスマッチを防ぐための対策4選
採用のミスマッチを防ぐためには、原因を正しく把握し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、今すぐ取り組める対策を4つ紹介します。
会社情報を発信する
採用のミスマッチを減らすには、企業の実態をできるだけ正確に求職者へ伝えることが大切です。業務内容や給与条件などだけでなく、組織文化や自社が抱えている問題、課題などのマイナス面も隠さずに伝えることで入社後のギャップを小さくできます。
このとき、SNSやオウンドメディアを活用するのがおすすめです。これらを使うことで、求人情報だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や従業員の本音を発信でき、企業の透明性や誠実さをアピールできます。さらに、企業が課題解決に取り組んでいる姿勢もあわせて伝えることで、求職者の共感を得やすくなり、ミスマッチ防止につながります。求職者が働く姿をしっかりイメージできるよう、多くの情報を発信することが重要です。
キャリアパスや報酬体系を明確にする
キャリアパスや報酬体系をはっきり示すことは、求職者が自分の将来を具体的に思い描くためにとても大切です。たとえば、昇進に必要な経験やスキル、キャリアアップを支える仕組みなどをきちんと示すことで、入社後の不安や誤解を減らせます。このとき、専門用語は避けて誰にでもわかる言葉で表現するのが望ましいです。
また、業務内容や労働時間などの基本情報も一日の業務スケジュールや残業の有無、頻度などの具体例を交えて伝えましょう。評価基準も明確化することで従業員定着率の向上が期待できます。
リファラル採用を導入する
リファラル採用とは、自社の従業員から知人や友人を採用候補者として紹介してもらう採用方法のことです。すでに働いている従業員に対し、自社が求めている人材を伝えておけるため、採用のミスマッチを防げます。また、リファラル採用なら社内に知り合いがいるため、採用候補者の不安が軽減できるのもメリットです。さらに従業員の人脈を通じて採用するため、採用工数を減らせて採用コストも抑えられます。
リファラル採用についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連する記事
採用アウトソーシングを活用する
採用のミスマッチを防ぐために外部の採用アウトソーシング(RPO)を活用するのもひとつの手です。自社で行う採用業務を外部委託することで、質の高い採用が期待できます。さらに採用活動は多くの手間とコストがかかりますが、実績のある採用アウトソーシングを活用すれば、その負担を抑えることが可能です。また、サービスによっては内定者に定期的なフォローを行ってくれるので、内定辞退や入社後の早期退職を防げます。とくに早期退職者が多い企業や大量採用する企業、人材採用のノウハウがない企業におすすめの方法です。
採用アウトソーシングならLHH
採用アウトソーシングの導入を検討中ならLHHがおすすめです。LHHの採用アウトソーシングなら、採用計画から内定した方のフォローまで、採用にかかわるすべての業務を代行できます。業務を担うのは業界や職種に関する高い専門知識を持った担当者です。この担当者が企業の課題やニーズを聞き取り、最適な業務フローを提供します。これにより、採用業務の効率化が図れ、採用難易度の高い人材の獲得も可能にします。
このようにLHHの採用アウトソーシングを活用することで質の高い採用活動を実現でき、採用のミスマッチの減少に貢献します。さらに内定者に対して定期的なフォローを行うため、内定辞退や早期退職を予防できます。
まとめ
採用ミスマッチは、企業と求職者間の認識の違いによって起こり、早期退職の原因になります。そのおもな原因は、求職者にデメリットも含めた情報提供が行われていない、採用基準が統一されていない、内定後のフォローが不足しているなどです。
このような採用のミスマッチを防ぐためには、企業情報の透明性を高め、多くの情報を発信することが重要です。また、リファラル採用や採用アウトソーシングを導入することも有効です。
採用アウトソーシングの導入を検討中なら、LHHの採用アウトソーシングがおすすめです。質の高い採用活動で、採用のミスマッチ防止に繋げます。
最新のセミナー情報、コラムなどを受け取りたい方は、下記からメールマガジンを登録してください。