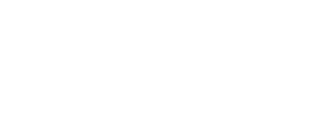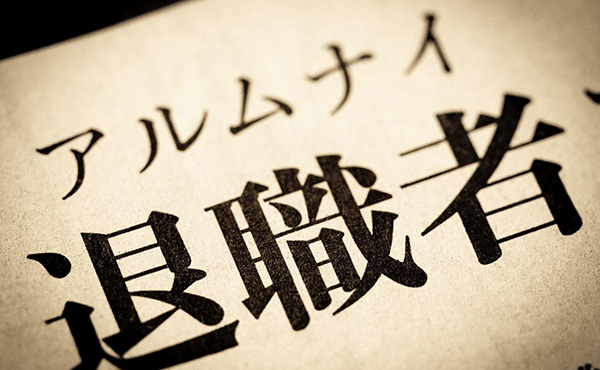ミートアップ採用とは交流会を活用した人材獲得術

ミートアップとは、共通の趣味や関心を持つ人々が集まる交流会全般を指します。元々はアメリカの企業が提供するプラットフォームの名称でした。
ミートアップ採用は、企業が求職者と直接交流し、自社の魅力を伝えることで、求人情報だけでは伝わりにくい社風や雰囲気を、参加者に確認してもらうことができます。また、必ずしも採用を前提とせず、企業の認知度向上やブランディングの一環として実施されるケースもあります。
ミートアップ採用には、企業と求職者が直接交流し、関係を深めるための主な形式として、「交流会型」「勉強会型」「説明会型」の3種類があります。
交流会型は、企業と求職者がカジュアルな雰囲気で自由に交流する形式です。雑談や質問を通じて企業文化や職場環境を伝えられ、リアルな職場の雰囲気を体感できます。幅広い層が参加しやすく、企業の認知度を高める方法としても有効です。
勉強会型は、特定のテーマに沿ったセミナーやワークショップを通じて求職者にアピールする形式です。エンジニアやマーケターなど、特定スキルを持つ参加者をターゲットにするケースが多く、実務に関心のある人材とつながる機会をもつことができます。この形式のミートアップでは、参加者に「この環境なら成長できる」と感じてもらうことが、採用に繋げるカギとなります。
説明会型は、企業のビジョンや事業内容、将来の方向性を求職者に伝える形式です。通常の求人情報では伝えきれない事業の詳細や社内の取り組みを共有することで、企業理解を深め、採用のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
ミートアップ採用では、目的に応じて適切な手法を選択することで、求める人材との接点の創出につながります。採用手法の最新トレンドについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
ミートアップ採用を実施するメリット

採用のミスマッチを減らせる
採用活動の際、求職者に会社の雰囲気が十分に伝わらず、入社後のギャップにつながることは少なくありません。
ミートアップでは、現役社員と対話したり職場の雰囲気を体験したりする機会があり、参加者はより深く企業を理解できます。仕事の進め方やチームの雰囲気を直接知ることで入社後のイメージを具体化でき、内定辞退や早期離職のリスクを軽減することが可能です。企業としても、自社の価値観に共感する人材を獲得しやすくなります。
このように、ミートアップ採用は参加者と企業の双方にとって、採用のミスマッチを減らす有効な手段です。
自社の認知向上やファンづくりに役立つ
参加者との距離感を縮め、企業の認知向上やファンづくりにも貢献します。
従来の就職説明会とは異なり、ミートアップでは企業と参加者がカジュアルな雰囲気の中で直接対話できます。現役社員との交流を通して、会社の雰囲気や職場環境、仕事内容をリアルに伝えられるため、企業の魅力をより深く知ってもらえます。Webサイトやパンフレットだけでは伝えきれない自社の魅力を、直接アピールする絶好の機会です。
また、少人数制が多いため、参加者一人ひとりとの密なコミュニケーションが可能です。企業のカルチャーや価値観を直接伝えることで、参加者の共感を呼び、入社意欲を高めてもらえます。
さらに、ミートアップでの交流を通じて、参加者が企業のファンになる可能性も高まります。イベント後に参加者が企業の魅力をSNSや口コミで発信すれば、ブランド認知の向上や新たな求職者の獲得につながる可能性があります。
採用コストを抑えやすい
開催場所や方法を柔軟に選べるため、コストを抑えて実施できる点もミートアップ採用の特長です。基本的に少人数で開催するので、自社のオフィスや小規模なレンタルスペースでも十分開催が可能です。就職説明会のように大規模な会場を用意する必要がなく、開催費用を削減できます。また、オフィスで開催すれば、企業の雰囲気を直接体験してもらえるというメリットもあります。
さらに、開催費用を抑えられれば開催の回数も増やせて、より多くの参加者との接点を持てます。
そのほか、オンライン開催も選択肢のひとつです。遠方からの参加者や忙しい参加者にも配慮した形で、コストを抑えつつ広範囲の人材と交流できます。
ミートアップ採用を実施する際の注意点
担当者の業務負担が増えやすい
企画から開催まで自社で進めるため、担当者の業務負担が増えやすい点に注意が必要です。効果を高めるには継続して開催することが重要ですが、参加者を飽きさせないためにも毎回異なる企画を考える必要があるからです。
また、企画の内容によっては社内の人材や上層部の協力が必要なケースもあり、依頼や調整業務が煩雑になることもあります。業務が集中すると、通常の採用業務にも影響を及ぼしかねません。
負担の軽減には、開催頻度を調整することや、採用支援サービスなどを活用して業務の一部を外部に委託することも有効な対策となります。
必ず採用につながるとは限らない
ミートアップ採用は、必ずしもすぐ採用につながるわけではありません。この手法の目的はまず参加者に自社への興味を持ってもらうことであり、応募や選考を前提としていないからです。
参加者もミートアップを気軽なイベントと捉えているので、入社意欲の高い人ばかりが集まるわけではありません。企業側は長期的な視点を持ち、定期的に開催しながら関係を築くことが求められます。
採用につなげる確率を高めるには、テーマや内容を、特定のスキルや志向を持つ層に絞るのが効果的です。ターゲットを明確にすることで、応募の可能性を高められます。
また、効果が見えにくいと、運営側のモチベーションが下がることもあるため、工夫が必要です。たとえば、イベント後のアンケートを実施してフィードバックを収集し、次回の内容に反映することで、より有意義なミートアップに改善できます。
ミートアップ採用の実施方法

ミートアップ採用を成功させるためには、事前の準備と継続的な改善が重要です。以下のステップに沿って進めると、スムーズな運営が可能になります。
1. 目的やテーマを明確にする
どのような人材を採用したいのか、開催目的を明確に決めることが重要です。「エンジニア採用のための技術交流会」や「社風を知ってもらうためのカジュアルな座談会」など、イベントの方向性をはっきりさせることで、ターゲットに合った内容を設計できます。
2. 集客する
開催目的に沿ったターゲットにリーチするため、効果的な集客方法を選択します。SNSや自社のオウンドメディア、転職サイトなどを活用するのが一般的です。ミートアップ採用専門のオウンドメディアを立ち上げるのもよいでしょう。
3. 準備する
会場準備や資料作成を行い、必要に応じて食事の手配も行います。また、当日のタイムスケジュールを綿密に計画し、円滑な運営を目指します。可能であれば、登壇者のリハーサルを実施し、運営スタッフの役割分担も事前に決めておきましょう。
4. ミートアップを開催する
参加者とのコミュニケーションを重視し、一方的な説明にならないよう工夫しましょう。質疑応答の時間は長めに取ると、参加者の疑問や不安を解消できます。
5. 結果の評価と改善を行う
終了後、参加者へのアンケートを実施し、イベントの満足度や改善点を分析するのがおすすめです。データをもとに改善を重ねることで、より効果的なミートアップへとブラッシュアップできます。
ミートアップ採用を成功させるポイント
ミートアップ採用を成功に導くためには、いくつかの重要なポイントがあります。とくに、効果的な集客戦略の立案が成功のカギを握ります。
さまざまな媒体で集客を行う
ミートアップ採用を成功させるには幅広い告知が不可欠です。SNSに加え、地域コミュニティに特化したMeetupやイベントツール「connpass」などのイベントプラットフォームを活用することで、ターゲット層に適した集客が可能になります。
利用者層に違いがあるため、複数メディアで告知を展開すると、より多くの求職者にアプローチできます。
自社メディアのフォロワーやアクセス数が少ない場合は、転職サイトや採用イベントプラットフォームを併用してみましょう。
小規模のミートアップを定期的に開催する
ミートアップ採用は、小規模での開催が効果的です。少人数制での密度の高い交流により、企業の魅力を深く伝えやすくなります。
加えて、定期的な開催も重要です。参加者が企業と継続的に接点を持てるようになれば、応募や採用につながる可能性が高まります。大規模な説明会のような形式ではなく、参加者一人ひとりと丁寧に交流することが大切です。
応募者多数の場合は規模を拡大するよりも小規模な開催を継続することで、参加者同士のコミュニケーションを促せます。採用につながるコミュニティ形成を目指しましょう。
参加者に対するアフターフォローを行う
開催後は、参加者との関係を維持するため、アフターフォローを徹底することが重要です。アンケート送付やイベント情報提供などで、結び付きを保ちましょう。
アンケート回答結果から、自社に関心の高い参加者を企業説明会や面談に招待するのも有効です。アフターフォローを通して次回の参加を促し、継続的な関係を構築することで、採用につながる可能性が高まります。
ミートアップ採用の活用には、戦略と運用体制の両立が不可欠
ミートアップ採用は、求職者と直接交流できる点が魅力の採用手法です。企業の雰囲気や価値観をリアルに伝えることで、ミスマッチの少ない採用を実現しやすく、自社のファンづくりにもつながります。また、採用コストの抑制という面でも注目されています。
ただし、イベントの企画・運営、集客、フォローなどにかかる業務負荷は決して小さくありません。
社内リソースが限られている企業にとっては、継続的な運用が難しくなったり、通常業務に支障が出たりするケースも少なくないのが現実です。
そんなときこそ、LHHの採用代行(RPO)サービスが力になります。
採用戦略の立案から、母集団形成・候補者対応・選考調整まで、LHHのプロフェッショナルチームが一括して支援。採用担当者の負担を大幅に軽減しながら、採用成功の精度とスピードを両立します。
採用業務のリソース不足や運用負担にお悩みの方は、LHHにご相談ください。